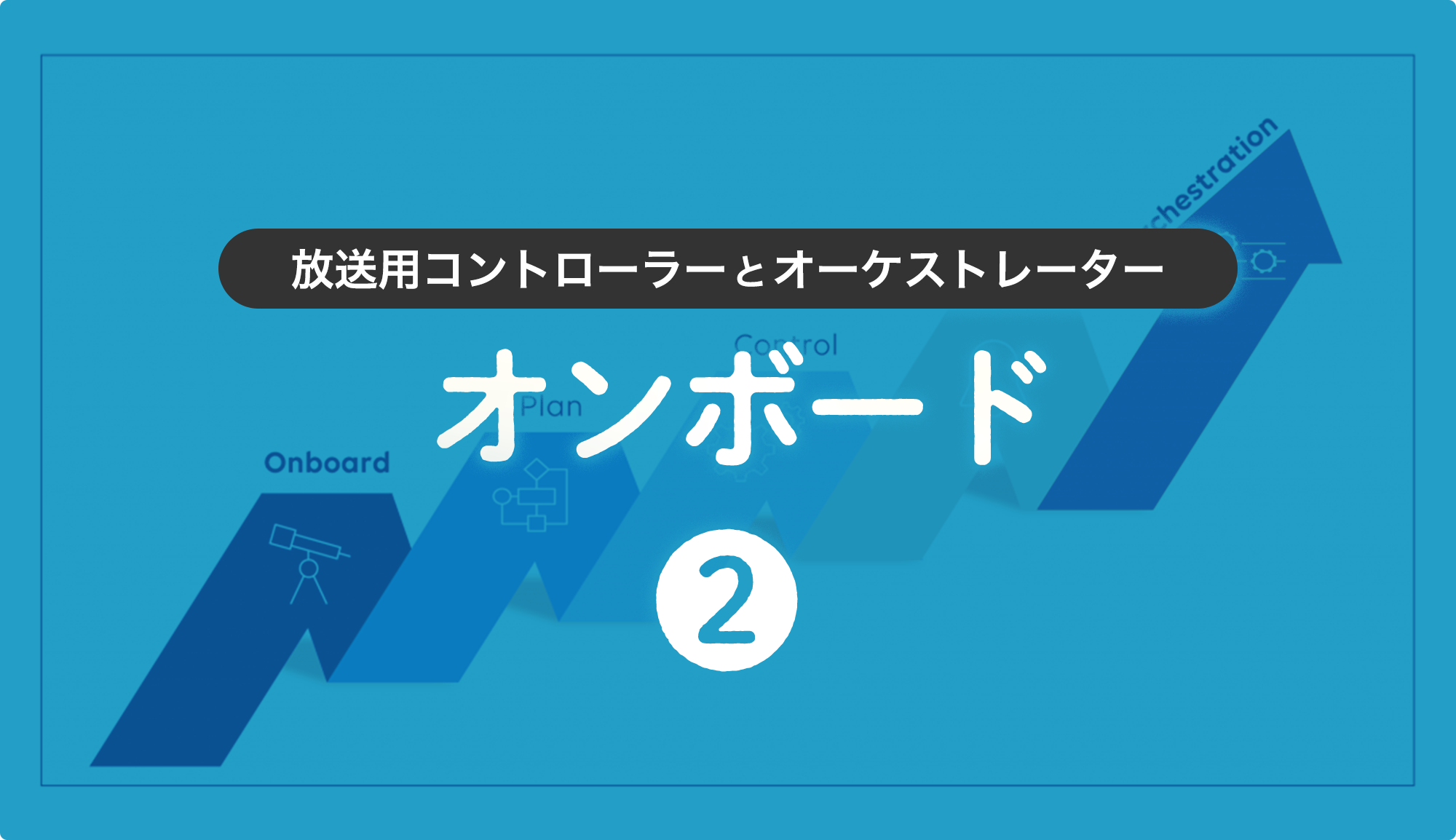前回の振り返り
- SDNコントローラーとブロードキャストコントローラーの違いを整理
- オーケストレーションレイヤーの必要性と全体像を紹介
前回は「コントローラーとオーケストレーターの違い」や、「IP化に伴って変化する制御の構造」について見てきました。 このブログでは、オーケストレーションの最初のステップである「オンボーディング」について見ていきましょう。

オンボーディングとは何か?
「オンボーディング(Onboarding)」とは、ネットワークやオーケストレーションプラットフォームに対して、新しいリソース(機器・サービス)を登録し、利用できるようにするプロセスのことです。
目的
- 安全かつ自動的に機器を検出・初期設定する
- 認証・確認された機器のみを「使用準備完了」状態として管理する
具体的なステップ
1.検出:
- NMOS IS-04レジストリ、LLDP、ネットワークスキャン、CMDBなどを用いて機器を自動認識
2.初期設定と検証:
- ファームウェア・ソフトウェアのバージョン確認
- 必要な設定テンプレートの適用
- 標準認証情報の更新確認など
3.使用可否ステータスの判定:
- 「使用準備完了」かどうかを常に追跡し、コンディション変化に応じて動的に管理
使用準備完了に影響する要素
オンボーディングが完了していても、以下のような状況で「使用準備完了」のステータスが変動する場合があります。
- 故障やアラームの発生(例:AIによる予兆検知)
- 保守期間中のリソース
- セキュリティ脆弱性の検出
- 使用権限やライセンス状態の変化
なぜオンボーディングを自動化するべきか?
- 一貫性の確保:人手による設定ミスを防ぎ、品質を安定化
- セキュリティの強化:認証されたリソースのみが接続可能
- 効率性の向上:プロジェクト開始時の初期設定作業を大幅に短縮
SDN/BCコントローラーとの連携
オンボーディングされたリソースの情報は、オーケストレーターだけでなく、SDNコントローラーやブロードキャストコントローラーとも共有する必要があります。
- 使用可能リソースリストのAPI連携
- IPアドレスやマルチキャストアドレス範囲の共有
- コントローラーが必要とする情報をオーケストレーターが一元管理
今回のまとめ
- オンボーディングは、機器を安全かつ自動的に登録し「使用準備完了」として管理するプロセス
- 検出・初期設定・確認のステップで構成され、動的に状態が変化する
- 健康状態や権限、ライセンス、予測アラームなどが「使用準備完了」に影響
- 自動化により、一貫性・セキュリティ・効率が大幅に向上
- オンボーディング情報は、他のコントローラーとのスムーズな連携の鍵となる
結論と次回予告
オーケストレーションの第一歩は、信頼できる情報源からすべての機器を正しく登録し、状況に応じた制御が可能な状態を保つことです。
この仕組みが整って初めて、「計画的なリソース活用=プラン」へと進むことができます。
次回(第3回)は、リソース予約とイベント設計のための「プラン」ステップについて掘り下げていきます。
製品情報